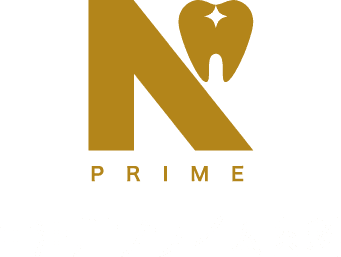予防歯科では、虫歯や歯周病になってから治療するのではなく、それらの病気を予防するための治療を行います。病気になってから治療をしたとしても、失ってしまった歯や歯茎は元には戻りません。だからこそ、しっかり予防していくことが大切なのです。

こちらのグラフは、定期的に歯科検診やクリーニングを受けている人の割合を、スウェーデン・アメリカ・イギリス・日本で比較したものです。
スウェーデンでは9割、アメリカでは8割、イギリスでも7割の人が、予防のために歯科医院へ通っています。
一方、日本ではわずか5パーセントと、大きな差があります。
この違いは、国ごとの「予防に対する意識」の差を表しています。
日本でも、少しずつ予防の大切さが知られるようになってきましたが、まだ十分とはいえません。
歯は、治療するよりも、守るほうがずっと簡単で負担も少なくてすみます。
痛くなる前に通うという新しい習慣を、私たちと一緒に始めてみませんか。
こちらのグラフは、80歳時点で残っている歯の本数を、各国で比較したものです。スウェーデンでは20本、アメリカは17本、イギリスでも15本の歯が平均して残っています。
一方、日本はたったの8本という結果になっています。
この差の背景にあるのが、「予防の習慣」です。定期的に歯科検診やクリーニングを受けることが当たり前になっている国では、年齢を重ねても多くの歯を健康に保つことができています。
歯を失う原因の多くは、むし歯や歯周病といった予防できるものです。だからこそ、早めのケアが何よりも大切です。

PMTCとはProfessional Mechanical Tooth Cleaningの略で、直訳すると「専門家による機械を使った歯の清掃」という意味になります。様々な専用機器を使用して、虫歯や歯周病の最大の原因である「バイオフィルム(歯の表面についた細菌のかたまり)」や歯垢・歯石を除去していきます。あくまで歯のクリーニングなので、ドリルなどで歯を削ることはありません。
普段の歯磨きでは除去できない汚れが取れますので、爽快感を味わうことができます。バイオフィルムは約3ヶ月で再生されると言われていますので、定期的なPMTCをおすすめしています。
医院で歯に高濃度のフッ素を塗布します。フッ素を定期的に歯の表面に塗布することで、虫歯になりにくい歯を育てていきます。充分な効果を得るためには、年に3~4回のフッ素塗布を行うことが理想です。
01.
歯を強くする
歯のエナメル質を硬くすることで、虫歯の原因菌が作り出す酸に強い歯を作っていきます。
02.
再石灰化作用を助ける
酸で溶けてしまった虫歯になりかけた部分をもとに戻す、唾液の再石灰化作用を助けます。
03.
再石灰化作用を助ける
虫歯の原因菌の活動を抑えて、歯を溶かす酸が作り出される量を抑制することができます。

歯周病は、日本の成人の約80%が感染しているとても身近な病気です。
歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、歯茎が腫れたり、出血したり、最終的には歯周組織が破壊されて歯が抜けてしまう病気です。歯肉炎、歯周炎とも呼ばれています。
歯垢(プラーク)は時間が経つと歯磨きでは取り除くことができない歯石になります。歯石自体は歯周病の原因ではありませんが、歯磨きでは除去できないため周囲のプラークの除去を困難にし、専門的な治療が必要となるケースがあります。
STEP 01.
歯周ポケット診査、レントゲン撮影、口腔内写真撮影
歯周病の原因は一人ひとり異なりますので、治療していく前に検査を行い、それぞれに適した治療を行なっていきます
STEP 02.
プラークを除去
歯周病の原因は歯垢(プラーク)なので、プラークを除去して付きにくくすることが治療の基本となります。歯科衛生士による歯磨き指導や歯間ブラシ、デンタルフロスなどで改善をはかります。簡単に落とせる歯石やプラークを落していき、検査にて改善を確認します。軽度の歯周炎の方はここまでで治療が完了します。
STEP 03.
歯と歯肉の間に溜まっていた歯石や歯垢(プラーク)除去
中等度~重度の歯周炎の場合、歯石が深くまであるため取りきれません。このような場合は外科的な治療が必要となります。麻酔をしてから歯肉の切開をし、歯と歯肉の間に溜まっていた歯石や歯垢(プラーク)を除去します。
STEP 04.
メインテナンス
口の中の細菌を完全になくすことは難しく、歯周病は再発し易いので、治療完了後も定期的なメインテナンスが必要となります。再発防止には患者さま自身による歯垢(プラーク)のコントロールだけでなく、定期的に歯科医師や歯科衛生士による検診や治療を受け、歯をメインテナンスすることが重要です。